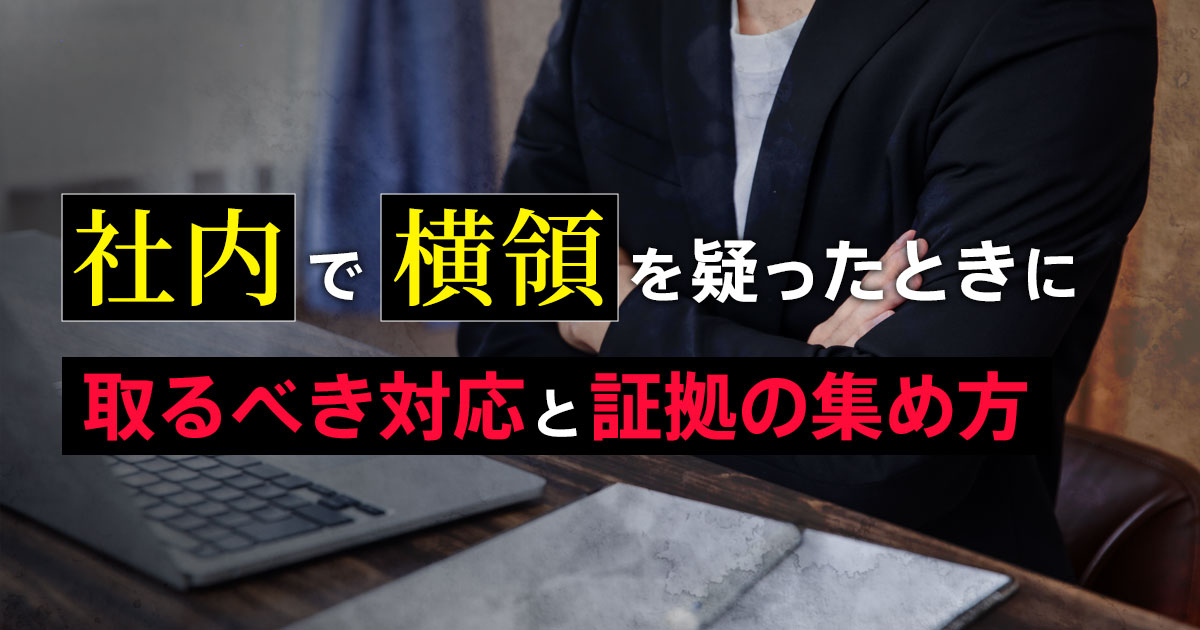目次
企業内の信頼関係を揺るがす問題の一つに「横領」があります。日々の業務の中でふとした違和感を覚えたとき、それが実は重大な不正のサインだったというケースも少なくありません。しかし、横領は巧妙に隠されていることが多く、表面化したときには既に多額の損失や人間関係の崩壊を招いてしまっていることもあります。特に社内の人間関係が密な企業ほど、疑念を口にすることを躊躇してしまいがちです。本コラムでは、横領の背景やサイン、冷静な対処法を、実務視点でわかりやすくまとめました。
もしかしたら、自社でも起きているかもしれない。そんな不安を感じたときこそ、ぜひ最後までお読みいただき、冷静な一歩を踏み出すための参考にしていただければ幸いです。
社内で横領が起きる典型的なケースとその背景

企業内での横領は、信頼を裏切る重大な背任行為であり、発覚したときには会社全体に大きなダメージを与える可能性があります。特に中小企業においては、経理や会計などの重要業務を少人数で回しているケースが多く、不正が起こりやすい環境が生まれてしまうことも少なくありません。ここでは、実際に横領が起こりやすい典型的な状況を、より具体的に見ていきましょう。
現金や物品を扱う部署での管理体制の甘さ
【店舗運営部での横領】
現金や物品の管理が現場任せになっていると、不正が発覚しにくくなります。たとえば、レジ締めや在庫の確認が担当者の判断に任され、上司や第三者のチェックが入らない場合、少額の金銭や物品の横領が日常的に行われていても気づきにくくなります。特に繁忙期などは管理体制が甘くなりやすく、業務の流れの中で不正が隠れやすい状況が生まれます。こうした現場任せの状況が続くと、管理の形骸化を招き、不正が組織に根づいてしまうリスクにもつながります。
具体的なリスク要因
- レジ締め作業のチェックが形式的になっている場合
- 出納帳や在庫管理の記録に定期的な照合作業がない場合
- 監視カメラや管理者の立ち会いなどの抑止力が機能していない場合
こうした環境では、業務に紛れて少額の横領が繰り返され、長期にわたり発覚しないケースが珍しくありません。
経理担当者が業務を兼任している場合のリスク
【名義だけの発注先】 中小企業の経理担当者が、実在しない架空の取引先を登録し、備品発注名目で定期的に振込を行っていました。実際にはその口座は自分名義の別口座で、月10万円ほどを横領していたことが発覚しました。きっかけは「実際には納品されていないのに請求書だけが上がっている」と現場社員が不審に思ったことからでした。
職務が一人に集中していると、その人の判断だけで大きなお金を動かせてしまう状況になります。
特に注意すべき業務パターン
- 発注書の作成から請求書のチェック、支払い処理までを一人が行っている場合
- 支払い先が実在するか、納品が正しく行われているかを確認する仕組みがない場合
- 役員や上司が細かい支出まで目を通していない場合
内部牽制が機能しない状態では、不正が起きたとしても、その痕跡は巧妙に隠されてしまいます。
信頼による油断が招く不正の盲点
【功労者による裏切り】 管理部門の課長職として長年勤めていた社員が、出張旅費や交際費の精算をごまかしていた事例もあります。領収書の金額を水増しして経費精算を行い、数年で合計100万円以上を不正に取得しました。本人は「少額だから問題ないと思っていた」と語ったものの、経営陣にとっては大きな裏切りでした。
背景にある組織の油断
- 「この人に限ってそんなことはしない」という思い込みがある場合
- 社歴や功績への遠慮から、業務のチェックが甘くなる場合
- 不正の兆候が見えても、指摘しづらい空気が社内にある場合
これらのケースは、いずれも「チェック機能の欠如」や「信頼の過信」が存在します。会社の規模や業種に関係なく、内部統制を見直す機会を定期的に設けることが、横領防止の第一歩となるでしょう。
横領の兆候として現れる社内の不自然な変化
社内で「何かおかしい」と感じた瞬間が、不正の発見につながることがあります。ただし、直感だけで動くのではなく、具体的な行動の変化や数字のずれに注目することが大切です。ここでは、横領の初期兆候としてよく見られる具体例を解説します。
不自然な残業や休日出勤が増えたとき
勤務時間の異変は、何かを隠そうとしているサインである可能性があります。たとえば、明確な業務内容や指示がないにもかかわらず残業が続いている場合、その時間に帳簿の改ざんや不正なデータ操作が行われていることも考えられます。また、深夜や休日といった他の社員がいない時間帯に限って出勤している場合は、目撃者を避けるための工作である可能性も否定できません。特定の社員だけが頻繁に「残っている」「早く来ている」といった状況があれば、その目的を丁寧に確認することが重要です。
注目すべきポイント
- 明確な理由のない残業や休日出勤が続く場合
- 他の社員が帰った後に一人で作業していることが増えた場合
- タイムカードの記録と実際の勤務時間にズレがある場合
とくに月末や締日の前後でこうした勤務が増える場合、何らかの処理や改ざんが行われている可能性もあります。業務内容に比べて、社内に長時間残っている様子があれば注意を向ける必要があります。
経費精算や在庫記録のズレが続く場合
書類や帳簿と実態のズレは、不自然な点の一つです。
たとえば、申請された経費と実際の出張日数が合っていない、在庫記録と現物が一致しない、請求書が複数回発行されているといった事例が該当します。特に、少額の不一致が繰り返されている場合は要注意であり、これが“氷山の一角”として大きな横領の前兆であることもあります。帳簿と現実の差異は、早期発見につながる有力なサインの一つと言えるでしょう。
よくある不自然な傾向
- 領収書の金額や枚数が多すぎる、日付が連日続く場合
- 社内の在庫と記録が一致しない場合(例:備品が足りない)
- 通常では必要のない経費や仕入れが発生している場合
また、特定の取引先や仕入先とのやり取りだけに異常が集中している場合は、その関係性自体を見直す必要があります。担当者と取引先の個人的な繋がりが背景にあるケースもあるため、疑問が生じた時点で過去の帳簿ややり取りをさかのぼって確認することが大切です。
生活水準が明らかに給与と見合わないと感じたとき
急激な生活の変化も見逃せないサインの一つです。たとえば、これまで公共交通機関で通勤していた社員が急に高級外車で通勤しはじめたり、平日は地味な服装だった人が急に高級ブランド品を複数身につけて出社するようになったといったケースがあります。さらに、社員間の会話で「最近マンションを購入した」「投資で儲かった」などの話が唐突に出てくるようになった場合も注意が必要です。もちろん、生活の向上には正当な理由があることもありますが、業務内容や給与とあまりにもかけ離れた変化であれば、周囲としては一度冷静に状況を見つめ直すことが求められます。
観察すべき行動や変化
- 高級車の購入や頻繁な海外旅行など、明らかに収入とかけ離れた消費行動がある場合
- SNSなどで派手な生活をアピールしている場合
- 給与明細や業務内容と比べて、生活レベルが著しく乖離しているように感じられる場合
これらの「違和感」は、見逃さずにメモを残しておくことが重要です。複数の兆候が重なることで、不正の全体像が見えてくるケースもあります。判断を急がず、記録に残しながら客観的な視点で対応を進める姿勢が、不正を早期に明らかにする第一歩になります。
横領を疑う前に知っておきたい思い込みの危険性
社内の不正を疑うとき、疑念を持つこと自体は重要ですが、それが思い込みや誤解である場合もあります。実際には業務上の正当な理由がある行動だったり、人間関係の感情が先行してしまうことで、誤った判断に陥ることも少なくありません。誤解によって社員との信頼関係を損なう前に、冷静に確認することが求められます。
業務上必要な行動が誤解されやすいケース
不正と誤認されやすい行動の中には、業務の性質上当然のことも含まれます。たとえば、営業職が複数回にわたって高額な接待費を使っている場合や、開発部門の社員が休日に出社し、機密情報を扱っている状況などは、ほかの部署から見ると『怪しい』と感じられても実は正当な業務の一環であることがよくあります。また、大口取引や緊急対応の前後には、物資の大量搬入や経費の急増が一時的に発生することもあり得ます。こうした背景を理解せずに「不審だ」と判断してしまうと、かえって信頼関係を損ないかねません。
具体的な例
- 機密性の高い情報を扱う部署で、夜間や休日に作業を行う場合
- 顧客対応で接待費や交通費の発生が多くなる営業職の場合
- 大口取引前の大量発注や備品の事前搬入などがある場合
こうした行動を『怪しい』と決めつけてしまうと、業務に支障をきたすことがあります。行動の背景を丁寧に確認する姿勢が重要です。
感情的なバイアスによる思い込みに注意
「嫌いだから」「なんとなく怪しいから」といった感情が先に立つと、冷静な判断を妨げます。人間関係のトラブルや嫉妬、性格の不一致などが原因で個人に対する偏見が生まれてしまうと、その人物の通常の行動も、必要以上に疑わしく見えてしまうことがあります。たとえば、たまたま高額な経費を処理しているのを見かけた、他の社員と距離を取っているといった理由だけで「何か隠しているのではないか」といった先入観を持ってしまうことがあります。しかし、そのような誤解に基づく疑念は、無実の社員を傷つけ、組織の信頼を大きく損なうリスクがあります。
注意すべき感情的なバイアス
- 過去にトラブルがあった相手を無意識に疑ってしまう場合
- 自分と価値観が合わない社員を“何かしそう”と感じてしまう場合
- 周囲の噂や印象だけで判断してしまう場合
疑う前に「思い込みではなく、証拠に基づいた事実確認ができているか」を改めて見直してみることが大切です。
誤解による内部トラブルを防ぐためにも、「疑わしくない」行動を見極める目を持つことが、横領や不正の真実を見抜く上での重要な前提となります。
横領の疑いを持ったときに取るべき冷静な対応とは
横領の疑いが浮上した際、間違った対応によって証拠を失ったり、本人を刺激して逃げ道を与えてしまったりするリスクがあります。疑念を抱いたときこそ、感情に流されず、慎重かつ計画的に対応することが重要です。
感情に流されず事実確認を優先する
驚きや怒りから相手を問い詰めたくなる気持ちもわかりますが、感情的な言動は逆効果です。まずは冷静に、何が「疑わしい」のか、どのような証拠や状況があるのかを整理しましょう。
初期に確認すべき事項
- 帳簿や領収書の不一致箇所
- 他の社員の証言や違和感を持った発言
- 物品の在庫や金銭の記録との整合性
「疑念を持っている」段階では断定は禁物です。事実確認の段階にとどめ、感情的な発言は極力避けるよう意識しましょう。
これらの確認項目に加えて、過去のデータとの比較も重要です。たとえば、前年同月の支出と比べて異常に費用が増えていないか、特定の仕入先への発注が急増していないかなど、数値の変化から見える異常もあります。データの違和感は、主観ではなく客観的根拠として記録できるため、証拠としての信頼性も高まります。
社内での聞き取りは慎重に行う

聞き取りを行う際は、「取り調べ」にならないよう細心の注意を払う必要があります。過度に追い詰めたり、問い詰めるような口調では、本人に警戒され証拠隠滅や退職などの行動を引き起こしてしまうことがあります。
効果的な聞き取りのポイント
- 複数名(できれば管理職+第三者)での対応をしましょう
- 日常会話の延長線のような形で、違和感を尋ねましょう
- 記録を残し、事実関係を逐一整理しましょう
聞き取り内容は後の調査や判断材料として重要になりますので、メモや録音などで残しておくことも検討すべきです。ただし、録音は違法となる可能性があるため、事前に法律の専門家に相談することが推奨されます。
横領の証拠収集で注意すべきリスクと探偵活用の重要性
社内の不正を立証するには、感情や印象ではなく「証拠」が何よりも重要となってきます。しかし、証拠収集には多くのリスクや法律上の制限も伴います。ここでは、自ら証拠を集める際の注意点と、探偵事務所などの専門家を活用する意義について解説します。
違法な証拠収集がもたらすリスクとは
社内で不審な動きが見えたとき、自ら証拠を集めようとする人も少なくありませんが、注意が必要です。業務時間外に社員のデスクを勝手に開けたり、パソコンの履歴を無断で確認する行為は、プライバシー侵害や違法な監視と見なされる可能性があります。
具体的にリスクがある行為
- ロッカーや私物の無断確認:たとえ会社内であっても、社員個人の私物に許可なく触れることはプライバシーの侵害にあたる可能性があります。物証が見つかった場合でも、違法に取得された証拠は無効と判断される可能性があります。
- 社内ネットワークでの履歴追跡(上司の権限を超えたもの):IT管理者以外が無断でメールやアクセスログを確認すると、不正アクセス禁止法などの法令に抵触するおそれがあります。本人の合意や明確な就業規則の根拠がなければ重大な違法行為となりえます。
- 録音・録画の設置を本人に無断で行う:職場での録音・録画は、明確な業務目的や事前説明がない場合、盗聴や盗撮と見なされ刑事責任を問われることがあります。特に個人のデスクや更衣室・休憩室など私的空間での設置は違法性が極めて高くなります。
法律に抵触する手段で得た情報は、たとえ真実を示すものであっても、証拠としての効力が認められない可能性があります。
違法な手段で収集された情報は、不正を追及するつもりが、自社が加害者となってしまうという調査方法を誤れば、逆に自社が加害者と見なされる危険もあるため、十分な注意が求められます。
確実な証拠を得るためには探偵事務所の活用が有効
疑念が強まり、社内での調査が難しいと感じた時点で、探偵事務所などの専門家への相談が安全かつ確実な手段となります。探偵事務所は、法律に準拠した方法で証拠を収集し、後々の法的対応にも活用できる「使える証拠」を提供してくれます。
状況が深刻化する前に、専門家の力を借りることで、より冷静かつ適正な判断が可能になります。では実際に、探偵事務所へ依頼することでどのようなメリットがあるのでしょうか。次章では、探偵事務所を活用することによって得られる具体的なメリットをご紹介します。
探偵事務所に横領調査を依頼する企業側のメリット

横領や不正に関する調査は、社内の立場や人間関係が関与することで、どうしても感情的な対応や判断ミスが生じやすくなります。こうしたときこそ、第三者である探偵事務所の存在が心強い味方になります。ここでは、探偵事務所を活用するメリットについて具体的に紹介します。
社内の人間関係を壊さずに事実確認できる
横領の調査において、社内の人物が調査を行うと、他の社員に「疑っている」という印象を与えかねず、チームの雰囲気が悪化するリスクがあります。
本人への刺激を避けつつ、客観的な立場で調査を進められる点も、探偵事務所に依頼する大きなメリットです。
探偵による証拠収集のメリット
- 外部からの調査により関係者に気づかれにくい
- 適正な方法で証拠保全が行われる
- 丁寧に整理された報告書を作成してもらえるため、今後の方針を検討する際の参考としても使用できる
初期相談で調査の必要性を判断できる
探偵事務所では、「調査が本当に必要なのか」「どのような調査方法が適切か」などについても相談が可能です。
相談時点では「まだ確信が持てない」「モヤモヤする程度」といった曖昧な感覚であっても問題ありません。愛晃リサーチでは、調査の前段階から状況を整理し、どのような証拠が今後必要になるか、どの時点で本格調査に移行すべきかといった見通しも含めてアドバイスが可能です。
その後、調査のご依頼をいただいた場合も、内容や状況を丁寧にうかがいながら、一つひとつ確認を重ねた上で進めてまいりますので、ご不安な点があっても安心してご相談いただければと思います。
社内不正を防ぐために企業がまず取り組むべきこと
横領や不正が疑われる状況に直面したとき、最も重要なのは「慌てず、焦らず、冷静に事実確認を進めること」です。早まった判断や違法な調査は、逆に会社の立場を不利にしてしまう恐れがあるからです。
「社内で何かがおかしい」と感じたそのときが、最も重要なスタート地点です。慎重かつ理性的に状況を見極める姿勢が、企業にとって最善の道筋となるでしょう。
また、不正の疑いを放置すると、経営リスクだけでなく従業員の士気にも悪影響が及びます。「見て見ぬふりをされる会社」と感じさせてしまえば、真面目に働く社員ほど失望し、離職や信頼低下につながりかねません。逆に、しっかりと初動対応を行い、透明性を持って問題解決にあたる姿勢を示すことで、組織全体の安心感と信頼を育むことができるのです。
愛晃リサーチでは、企業調査の実績が豊富な専門相談員が、初めての方にも分かりやすく対応し、企業のリスクと真剣に向き合います。社内の信頼関係を崩さずに問題を解決へ導くサポート体制を整えております。